会社を一人で起業した場合、一定の制約(役員報酬の変更時期に注意!原則、期首から3ヶ月以内のみ可能)はあるものの、基本的には役員報酬を自由に決めることができます。
ここで気になるのが「役員報酬の金額に上限があるのか?」という点です。
極端な話、従業員や同業他社と比較して、50倍など青天井で役員報酬を増やしても問題ないのでしょうか?
この記事では、役員報酬の上限・限度額について解説していきます。
役員報酬が「不相当に高額」な場合は損金不算入
先に結論を言っておくと、役員報酬が「不相当に高額」な場合は、損金算入できません。
このことは、国税庁の公式サイトでも記載されています。
ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。
(注) 上記の給与からは、(1)退職給与で業績連動給与に該当しないもの、(2)左記(1)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するものおよび(3)法人が事実を隠蔽し、または仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。
出典:国税庁「役員に対する給与」
役員報酬が損金算入できないと、税金の負担が大きくなってしまうデメリットがあります。
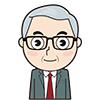
このとき、個人の税金(所得税や住民税)は、年収2,000万円として課税されます。
しかし、会社の経費として損金算入できるのは、税務署から認められた1,000万円だけとなり、その分、利益がかさ増しされ法人税の負担も増えてしまいます。
役員報酬の「不相当に高額」の基準
ここで気になるのが、役員報酬における「不相当に高額」の具体的な基準です。
実は、法律上で不相当に高額について「利益の○%まで」「従業員の給料の○倍まで」「同業他社の役員報酬の○倍まで」といった具体的な数値の定めはありません。
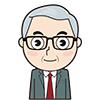
具体的な数値は決まっていなくても、
- 形式基準
- 実質基準
という大きく分けて2つの判断基準が設定されています。
形式基準
株主総会などの決議により定められている役員報酬の限度額
実質基準
- 役員の職務の内容
- 会社の収益
- 使用人に対する給与の支給状況
- 事業規模が類似する同業他社の役員報酬の支給状況
を照らし合わせて、役員報酬としての妥当性を判断
役員報酬の「不相当に高額」の法令と判例

ここからは、役員報酬の「不相当に高額」の法令と判例をまとめています。
法令
ここまで解説した役員報酬の「不相当に高額」については、法人税法で次のように定められています。
2 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
出典:法人税法第34条第2項
上記の条文にある「不相当に高額な部分の金額」は、政令(法人税法施行令)で規定されています。
第七十条 法第三十四条第二項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与(法第三十四条第二項に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)
ロ 定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により役員に対する給与として支給することができる金銭の額の限度額若しくは算定方法又は金銭以外の資産(ロにおいて「支給対象資産」という。)の内容(ロにおいて「限度額等」という。)を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員(当該限度額等が定められた給与の支給の対象となるものに限る。ロにおいて同じ。)に対して支給した給与の額(法第三十四条第六項に規定する使用人としての職務を有する役員(第三号において「使用人兼務役員」という。)に対して支給する給与のうちその使用人としての職務に対するものを含めないで当該限度額等を定めている内国法人については、当該事業年度において当該職務に対する給与として支給した金額(同号に掲げる金額に相当する金額を除く。)のうち、その内国法人の他の使用人に対する給与の支給の状況等に照らし、当該職務に対する給与として相当であると認められる金額を除く。)の合計額が当該事業年度に係る当該限度額及び当該算定方法により算定された金額並びに当該支給対象資産(当該事業年度に支給されたものに限る。)の支給の時における価額(第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額)に相当する金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(同号に掲げる金額がある場合には、当該超える部分の金額から同号に掲げる金額に相当する金額を控除した金額)
二 内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与(法第三十四条第一項又は第三項の規定の適用があるものを除く。以下この号において同じ。)の額が、当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
三 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したものの額
出典:法人税法施行令第70条
判例
過去の判例では、税務当局が酒造メーカーの「役員報酬」と「退職金」を損金不算入としたことにより裁判で争われました。
2016年の判決では、退職金については妥当と判断した一方、役員報酬については類似企業と比べて高すぎる(=不相当に高額)として追徴課税処分となりました。
この裁判で注目されたことが、月に1度も出勤していない”名ばかり役員”ではなく、実働のある役員に対しても役員報酬を一部否認したことです。
泡盛「残波」を製造する「比嘉酒造」(沖縄県読谷村)が、4年間に役員4人に支払った報酬や退職金計約19億4千万円が高過ぎるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(舘内比佐志裁判長)は22日、創業者の社長への退職金約6億7千万円については妥当と判断した。
その上で、報酬の全額を経費に算入して税務申告したのは誤りと判断した国税当局の追徴課税処分のうち、5千万円余りを取り消した。
比嘉酒造は2010年2月期までの4年間に、役員に支払った報酬と退職金の全額を経費として収益から差し引いて申告。沖縄税務署が11年6月、約6億円は法人税法で経費と認められない「不相当に高額な部分」に当たるとして約1億3千万円を追徴課税し、これを不服として提訴した。
訴訟で国は、九州南部と沖縄県で売り上げが同社の半分から2倍の酒造会社と比べ、金額が高過ぎると主張したが、判決は創業者の会社への貢献度を踏まえ、類似会社の最高額を超えていない退職金は妥当と判断。一方、同様に比較した役員報酬は高過ぎで、課税は適法と指摘した。
比嘉酒造側代理人の田代浩誠弁護士は「退職金についてはこちらの主張が認められたが、役員報酬に関する判断については主張が認められず遺憾」とコメント。会社側と相談して控訴するかどうか検討するとした。沖縄国税事務所は「主張が一部認められず残念だ」とコメントした。比嘉酒造の今年2月期の売上高は約20億円。
出典:沖縄タイムスプラス「泡盛会社創業者 退職金6億円「妥当」と判決」
最後に
役員報酬が類似企業と比べて「不相当に高額」な場合は、損金算入が認められない可能性があるので注意したいところです。
この記事を読んでいる方の中には「役員報酬を上げたいけど、大丈夫だろうか?」と心配されている方も多くいらっしゃるかと思いますが、なぜ、役員報酬を上げたいのでしょうか?
確かに役員報酬を上げれば、会社の利益を減らして法人税を下げることができます。
ただ、それにより法人税を下げることができても、それ以上に“個人の税金や社会保険料”が上がってしまえば、本末転倒です。
本当に大切なのは、会社の利益と役員報酬のバランス。
そして、社長ご自身が「どのくらいの役員報酬がほしいか」です。
確かに昔は法人税が高かったので、役員報酬を上げて利益を圧縮したほうが得になるケースも多かったですが、ここ数年は法人税が下がり状況が変わりました。
法人税と所得税は、累進課税によって税率が大幅に変わってきます。
だからこそ、役員報酬をいくらにすれば、「法人税と個人の税金・社会保険料の総支払金額が安くなるのか?」しっかりとシミュレーションする必要があります。
その場合は、税務の知識が必須となりますので、税務の専門家である私たちにご相談いただければと思います。
この記事の監修者
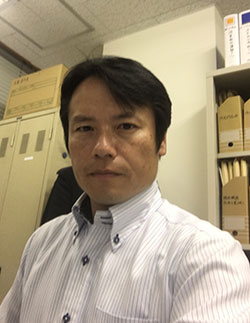
尾鼻 純
営業で多様なお客様と接する機会も多いですが、税金のことはもちろんのこと、あらゆる人脈を駆使してプライベートも含めたどのような相談にものれるよう心掛けております。これまで様々な困難な税務調査をクリアしてきました。税務署とは社長が納得されるまで徹底的に交渉させていただきます。
※本記事は、芦屋会計事務所 編集部によって企画・執筆を行いました。
※記事の執筆には細心の注意を払っておりますが、誤植等がある場合がございます。なお、執筆時から税法の改正等がある場合がございますので、最新の税法については顧問税理士等にご確認ください。


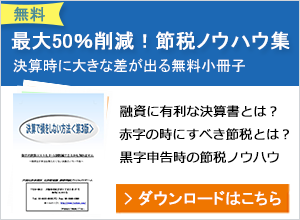
 近畿エリアで税理士をお探しならお任せください!
近畿エリアで税理士をお探しならお任せください!























